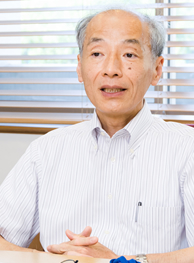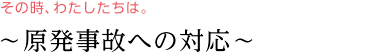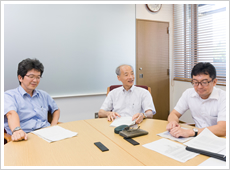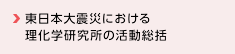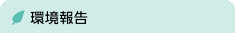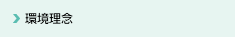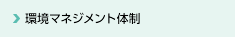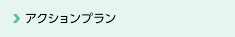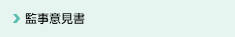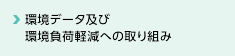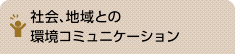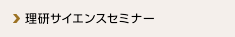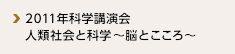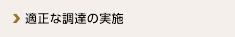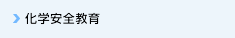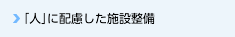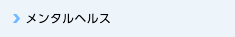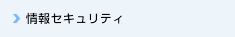- ホーム
- 特集
- Special Issue その時、わたしたちは ~原発事故への対応~
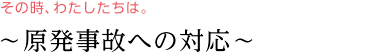
2011年3月11日の東日本大震災と、それに続く福島第一原子力発電所の事故。
放射性物質の飛散によって、日本中が不安を抱くなか、理化学研究所では放射線のスペシャリストたちが次々に福島へと向かい、被災地の復興を支援すべく活動を開始していた。その中心となったのは、原子核物理学の研究分野としては世界屈指の実験施設と技術力を持つ「仁科加速器研究センター」。
今回はそのキーマン3人に、当時の活動とその思いを語ってもらった。
上蓑 義朋(Yoshitomo Uwamino)
理化学研究所 仁科加速器研究センター 安全業務室長
羽場 宏光(Hiromitsu Haba)
理化学研究所 仁科加速器研究センター 応用研究開発室RI応用チーム・チームリーダー
和田 道治(Michiharu Wada)
理化学研究所 仁科加速器研究センター 実験装置開発室低速RIビーム生成装置開発チーム・チームリーダー
正しい情報、知識を提供するという困難
――震災が起きた直後の対応は?
上蓑:最初に文部科学省から「サーベイメーター(放射線測定器)が不足している。用意してほしい」という要請があったのが、3月13日の日曜日でした。私は文部科学省・原子力規制室の技術参与に登録されていましたから、その関係でしょう。理研の中を駆け回って10台を急いで揃えました。

上蓑 義朋氏
最初はお渡しするだけの予定でしたが、その夜に「福島へ搬送してもらえないか」と依頼を受け、急きょ現地に向かったのが14日です。私自身、原子核工学出身ということもあり、あの福島第一原子力発電所の事故を知り、このまま埼玉にいて良いのかなと自問していました。特別な使命感という気負ったものではありませんが、お役に立てればと。緊急車両登録等を済ませ、安全管理部の若手スタッフとともに福島県庁に着いたのが夕方です。現地はやはり非常に混乱していましたね。依頼されたことはサーベイメーターの準備と搬送でしたが、放射線量の測定のために数日現地に残ることとなりました。
和田:核物理学を研究していますので、事故発生当初から「ここで自分が何かしなければ」という思いがありました。そんなとき、核物理学研究者のコミュニティーで、何かチームとして行動できないかということが話題となり、決定したのが大阪大学が中核となり理研が基地となって関東や中部、関西、九州の研究者を集めて被災地で支援を行うことでした。福島県の緊急対策本部からは、現地での被ばくスクリーニングの人員が足りないという情報が入っていましたから、そのための人材支援をすることとなりました。
当時、東北地方の鉄道は不通でしたし、自動車のガソリンも手に入りにくい状況だったのですが、私が車両手配等のロジスティクス、大阪大学のチームが人員のスケジューリングを担当しました。第一陣が出発したのが3月21日。これを5月末まで継続して行い、理研からは延べ102人が参加しています。

和田 道治氏
――現地で測定をされて、いかがでしたか?
和田:福島県内の保健所や避難施設等で、住民や避難者の方に対して全身および一部甲状腺の緊急時スクリーニングを実施したところ、中には自衛隊に除染をお願いしなければならない程の汚染が着衣表面にあった方もいらっしゃいました。
普段からある程度の放射線量下で仕事をしてるわけですが、さすがに驚きました。
しかし、実際に身体への影響等を冷静に計算してみるとひどく高い数字ではありませんでした。最も心配されていたのは甲状腺への蓄積でしたが、私たちの測定で基準値を有意に超えた方は一人もいませんでしたので、少し安心しましたね。

福島県川俣町保健センターでの放射線スクリーニング
上蓑:私たち放射線を扱うプロならば、100?Sv(ミリシーベルト)以下の被ばくでは、広島、長崎のデータと比較しても身体への影響はあまり出ないという知識があります。放射線量は相当強いが、恐怖感を持つほどではないと。
しかし、福島市で得られる情報も東京とまったく一緒でさほど多くなく、情報源はテレビ位しかありません。現地の方々で、放射性物質や放射線についての知識のある方はそれほど多くないはずですから「直ちに影響はない」と言われても、内心穏やかではなかったと思います。
1年後の今、放射性物質やその影響に対して、避難されていた方々に正しい知識を広める工夫はもっと必要だったと思うところもあります。しかし、当時は現地で行政に携わる方々の中にも自身が地震で被災した方も多く、そんな中で必死にやっておられた。東京で見ているほど、関係者ができることは、そう多くなかったと感じています。
初動、そして横の連携の重要性
――羽場さんは、土壌や空気中の放射性物質の測定をご担当されました。3月11日以降の活動をお聞かせください。

羽場 宏光氏
羽場:3月15日の午前10時頃、普段研究を行っている埼玉県・和光市の加速器施設で、研究者が作業を終えて放射線管理区域から出ようとすると、ハンドフットクロスモニタ(汚染検査器)に次々とひっかかる。また、施設周辺の放射線レベルを監視しているモニタリングポストにおいて、空間線量率が増大しているという情報も入ってきました。実際に降下物や空気をサンプリングして、ゲルマニウム検出器で測定したところ、福島第一原子力発電所の事故起源と考えられる放射性物質がはっきりと検出されました。これは大変だということで、その後も継続的に大気の放射能濃度を測定することにしました。当然、理研(和光市)だけで測定するのではなく、広域情報を集めるために学会のネットワークを活用し、全国の大学や研究機関と連携して、1年間測定を続けました。
これによって、放射性物質がどのように拡散したかの情報が得られました。我々のデータは既に学会や論文誌で発表しています。そして、もうひとつの取り組みが、文部科学省が6月3日にスタートさせた福島県とその近隣の土壌汚染や空間線量率のマップをつくるプロジェクトです。

福島県での土壌サンプル採取の様子
私が所属する日本放射化学会や和田さんが所属する原子核談話会の研究者は、事故後早い段階で土壌汚染や空間線量率のマップ作成の組織を整えようとしていました。6月3日、それが文部科学省の支援を得て大プロジェクトとなってスタートできました。理研はそのプロジェクトに参画し、私がその窓口となりました。仁科加速器研究センターの研究者ら約30名に協力してもらい、集められた294の土壌サンプルを昼夜連続で分析し、約1,500の解析データを文部科学省に提出しました。
和田:惜しむらくは、もっと早くスタートできていたら一番大事なヨウ素のデータが取れていたことです。ヨウ素は人体で甲状腺に蓄積しやすい傾向があるのですが、半減期が8日間と非常に短いので、我々が測定をした頃にはヨウ素をほとんど検出できませんでした。これは、誰もがわかっていましたが、組織的に動くとなると研究者といえどもサンプル収集すら勝手にはできません。それが非常に残念ですね。
――上蓑さんは、福島で「放射線の基礎」など、一般の方に向けた講演をなさっていますね。
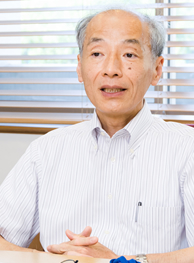
上蓑:やはり現地の方は不安を抱えていらっしゃいますから、福島では南相馬市で講演させていただきました。ベクレルやシーベルトの単位の説明や、自然界にもごく普通に放射性物質はあること。また、発がんのリスクなどについてです。
理研は中立的な立場ですので、私のようにまったく利害関係がなく、放射性物質への知識を持つ者がお話することが非常に大事だと感じました。1度目が好評で、2度目に南相馬の別の場所に行ったときは、「復興計画の第一ステップとして考えよう」「正しい知識を得てから、前に進みましょう」という、そんな受け入れ方をしてくださった。非常に身の引き締まる思いがしました。
和田:私は複数回現地に赴きました。スクリーニングのお手伝いをしているときには、現地の方々と1対1でお話する機会が多かったのですが、時間を経るごとに、非常によく勉強される様子がわかるようになりました。中には、明らかに誤った知識を持っている方もいたので、私のできる範囲で説明してさしあげましたが、なかなか伝わらず、歯がゆい思いもありました・・・。みなさん非常につらい思いをされているのに、私たちに感謝の気持ちを持って接してくださる方が多かったですね。そんな方々のためにも、もっと何か役に立てたのではないかという思いが今も募ります。
身体そのものの汚染は、時間を経るごとにほとんど検出されなくなりました。表面についた汚れは、お風呂に入ったり、服を着替えたりすることでなくなりますから。そうするとやはり気になるのは、水や食料の汚染はどうなのかということです。残念ながらそれを測定する装置はスクリーニングセンターにはなかった。この場合、羽場さんのネットワークなどをもっと早く生かしていれば、水や食物なども測定できたわけです。実際、後から羽場さんの装置を借りて現地でお預かりした飯館村の井戸水を測ったときには全く汚染がありませんでした。こういう動きが迅速にできていれば、とは思いますね。
科学者として何ができるのか
上蓑:私は日ごろ、仁科加速器研究センターで安全管理の部門を任されています。放射性物質を扱う研究が安全に遂行されるよう、過剰な被ばくや環境への影響がないよう細心の注意を払う仕事です。今回の一連の原発事故では、やはりメルトダウンに至ったのですから、危険に対して真正面から取り組んで対応してきていたのだろうか、と疑問をもたれても仕方ないと思います。「慣れてしまってはいけない」それは、ひとつの大きな教訓ですね。そして、もうひとつは、理研は国の予算で動いていますから、国家の緊急事態の場合は、いったん研究をストップしてでも全員で対応する姿勢も大事なのではないかと感じました。そうすれば、土壌や井戸水の汚染の測定なども、もっと迅速にできて今後に向けて有効なデータが得られたのではないかと。

和田:それは同感ですね。国内で理研は人員も設備ともに、それなりに整った組織だと思います。今回は、われわれ研究者が自主的に動いた部分も大きかったのですが、より組織的に動くことで、もっと貢献できることがあったのではないかと感じています。
一方で、今回の原発事故で放射線に関する知識や関心のなかった分野の違う研究者たちも、放射線に注目するようになっています。たとえば、友人に農学の研究者がいます。彼とは、ニワトリが汚染飼料を食べたときに、鶏肉へいくら移行するかといった研究を共同で始めました。既にこの研究は飼料の制限値をいくらにすれば適切かといったデータを提供するところまできています。こういう交流によって新しい分野が開ければ、社会にも貢献できると思います。
羽場:理研は、放射線を計測する技術について、世界最先端のものを持っています。そこで、民間の企業と一緒に、より使いやすく正確で安価な放射線測定器を作ろうというアイデアが、既に出てきています。これは、今後実現の可能性が高い事業になると思います。
上蓑:理研の良いところは、自由度が高いので個人の判断で動ける部分が多いことですね。今回の震災のときも、「ボランティアでも行きます」と志願した研究者はかなりおりました。仁科加速器研究センターでも何十名も福島に行きました。若い研究者の中には、阪神・淡路大震災のときには幼くて何もできなかった。「今度は一歩踏み出そう」という思いを持った者も多かったようです。
また、原子核や物理を研究する者として、原発事故に対して何か貢献したいという気持ちも強い。自分たちが担ってきた学問に責任があるという意識は強かったと思います。私自身も、和田さん、羽場さんもそうだと思います。
和田:我々にも何かできることがある!そんな気持ちですね。瓦礫の下から掘り出すような力はなくても、測ることはできる。そして、それを蓄え、今後に生かすよう繋げるのが使命なのかもしれません。